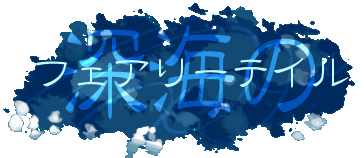猫。
一言で表すとしたらそういうものになるだろう。
機嫌の良し悪しは天気や朝の起こし方で気まぐれに経時的に変化し、悪気の無い善人を殺すこともあれば反吐を吐きたくなるような下品な悪人を笑って生かす。
海賊として最も大切な核芯はぶれずにその腹に据わっているから良いものの、それ以外については実に流動的で、つまりは大変に自分勝手な人間。
それが、が船長と仰ぐトラファルガー・ローという男だった。
ある日のこと。
が自室でソファベッドに仰向けになり、前の島で買ったハードカヴァーの童話を読んでいた時のことだった。
女だからと宛がわれた部屋の1/3を占める、ほかの全ての家具を諦めて手に入れた大きめのソファベッドはの唯一の城であった。
ノックも無しにその城へ侵入を果たした船長は誰がどうみても不機嫌そのものであり、は溜息を吐きながらもそのまま童話を読み続ける。
ただし彼がぎしりと音を立てながらソファベッドへ膝を乗り上げた瞬間から、の意識は既に童話という虚像の世界から低い唸りを上げる冷たい潜水艦へと引き戻されている。
乗り上げた船長がこちらに身体を伸ばしたのが見えて、はソファの上に立てていた膝を伸ばした。
スペースを空けないことで、船長の機嫌をますます損ねることを回避するためだ。
城への侵入を許された船長はずりずりと足元からこちらへの近付き、の身体に覆い被さるとそのまま腹の上に頭を乗せた。浅黒い腕が腰に周り、据わりのいい場所を探して船長の頭が動くものだからくすぐったさに思わず笑いが漏れた。
やがて一番いい場所を見つけたのか、ずれた柔らかな帽子をソファの下へ落とし腹に顔を埋めるようにして、ようやく一息つけたとでも言いたげに満足そうな息を零す。
「おい」
ここにきて、この部屋に初めて人の声がした。
低い呼び声に応えるべき人物は生憎と自分以外見当たらない。
はい、と短く返すとローが少しだけ顔を上げて、感情の読めない目をこちらへ寄越した。
「なんで何も言わねえ」
「いま、忙しいからです」
「お前は忙しいと男が馬乗りになってセックスしようとしてきても何も言わねえのか」
「しようとしているんですか」
「いや」
それきりまた船長は黙り込んで、のお腹に顔を埋めた。
特に話をするわけでもなく、何を命じるわけでもない。
どうやら船長は本当にただの腹の上で寝るためだけに此処に来たようだった。
腰に回った腕が時折蠢くのがくすぐったい。
の目は未だ文字列を追ってはいたが、そこに行儀よく並んでいる単語達はの頭の中へは入ってこなかった。
の静かな呼吸に合わせて船長の頭が揺れる。
意味なくページをめくる音と、ふたりの呼吸、それから海に締め付けられた船の音だけが響く空間は世界から切り取られた童話の1ページのようだ。
「…」
かすれた声がの名を呼んだ。なんですか、と返しても返答は無く、船長はただ腰に回した腕の力を一層強めるだけだった。
そこでようやく、鈍感なも気付いた。
このひとはただ甘えたいだけなのだと。
童話を開いたまま胸の上に置き、船長の濃紺の髪に手を移動させる。
いつもならば振り払われる筈の手でそのまま好きに船長を撫でられるという事実に、は自分の仮説が正しいことを確信した。
撫でる手に気分を良くしたらしい船長が満足げに息を吐く。
硬い髪を撫でる指は形のいい耳の後ろに到達する。
猫をあやす様にそこを緩くくすぐると、船長は額をの腹に擦り付けた。
手を前に移動させ顎に生えた髭に指を伸ばすと、横を向いた唇がの手に触れる。
彼の唇は乾燥し、ひび割れて指を引っ掻いた。
「船長、かわいい」
「ねむい…」
噛み合わない会話はいつものこと。
珍しく可愛い反応をしてくれる船長を抱きしめてキスしてやりたくなったが、残念ながら気紛れな猫はの腹をたいそう気に入り、そこから動きたくはないらしい。
ハードカヴァーの重い本を、ソファの横のサイドボードへと移動させる。
愛と冒険と希望ともの悲しさ、それから少しの不気味さと理不尽さを詰め込んだ子供の物語は革の表紙に押し潰されて、この潜水艦を舞台にした童話の世界から退場することとなる。